- 親書には流行りがある
- 親書は自己啓発本・体験記だけじゃない
- 親書は単行本と違って場所を選ばず気軽に読めるサイズ
- 一冊の親書を片手に課題を乗り切ろう
親書を読むことになった経緯

どうも。日ごろレポートに追われる、CanChanです

おいおい、こんなところで道草食ってないで、やることやったらどうなんだ

記事制作もやることの一つですよ
そう、「やりたい事」のなかでも、「物理的に難しいこと」と「やろうと思えばいつでもやれる」ってありますよね。
特に「やろうと思えばいつでもやれること」が降り積もると次第に手がつかなくなり、「物理的に難しいこと」に変化してしまいます。
そして私は、「環境問題にまつわる制作の記述」、「記事の制作」をやりたいと考えました。


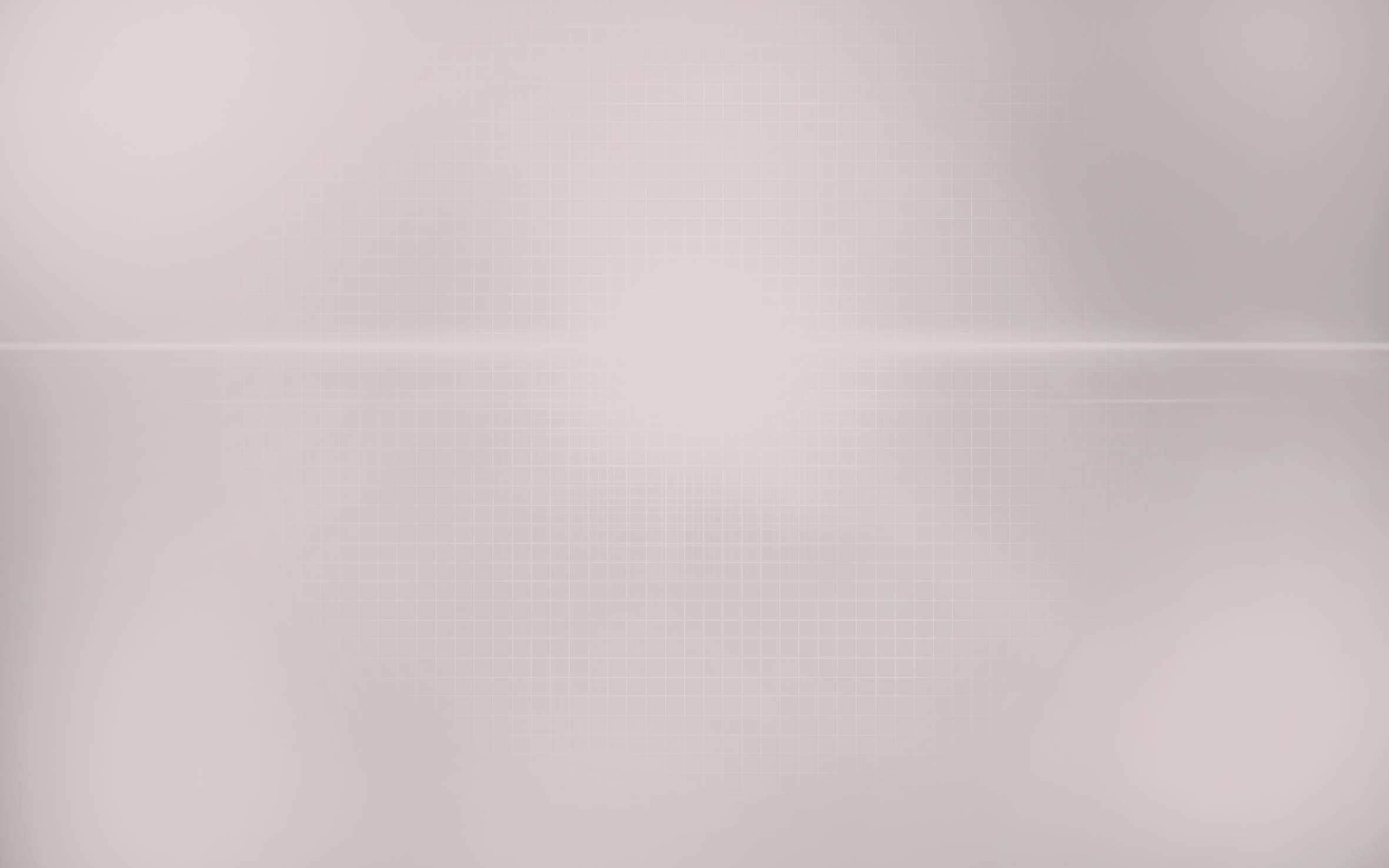

同時にやりたいことリストを消化すればいいじゃん!!
この天才的な発想により、制作物の記述と記事作成を同時にやり遂げることで、私は新たな次元へステップアップします。見ててください。

でも、どうやって二つ同時に消化しようか


あっ、そうだ。アレならいける
そんなこんなで、思いついたアレとは↓
だららららら
らららららららららら
らららっらららっらららららららら……
ジャン!!!!
[su_animate type=”slideInDown” duration=”2″ delay=”0″]
一度も読んだことがない
『親書』
のなかでも、非常に心が惹かれるタイトルの親書
前野ウルド浩太郎(2017). 「バッタを倒しにアフリカへ」 株式会社光文社
[/su_animate]
親書は流行りに敏感

私、親書は一度も読んだことありません
しかし、「とある事情」によりどの本が売れているだとか、どの本が売れやすいだとかはなんとなく理解しています。
ところで最も売れやすい本ってなんだと思います?

まぁ…面白そうなやつかな

……おしい?

なぜそこで断言できない

正解は~~、「流行っている本」でした
特に本の中でも親書は新鮮さが大切になります。
ジャンルとしては自己啓発やビジネス本が多いのですが、そのようなジャンルは「情報が命」ですから、新しい本ほど情報源として優秀と言えます。
そして何よりも表紙の「無骨さ」が文庫本よりも目立ちます。
人を選んでしまい、売れるのに時間がかかります。
以上のように親書はこのような状況に置かれていますから、結局何が売れるのかと言えば「流行っている本」になるのです。
売れるから流行っているとも言えますが、その逆の要素の方が強いと私は考えます。

CanChanの経験談でした
実は、自己啓発・ビジネスだけじゃない広いジャンル

本屋に足を運んだ時に、親書コーナーって目が滑りますよね

一瞬で通り過ぎて、文庫本のコーナーに行く
どれも同じことを言っているようなタイトルで、やたら辛気臭いというべきでしょうか。
でも面白そうな本がたくさんあるんですよ。
もし本屋に行く機会があれば、「講談社現代新書」とかあたりを散策してみてください。
比較的「近寄りやすいタイトル」が並んでいるので、そこそこ暇つぶしができます。
[su_animate type=”fadeInUpBig” duration=”1″]

[/su_animate]
手に収まるサイズ


電車やバスの中で読みやすい。これは大きなメリットです
例えば、家に帰る合間に読み込む。
すると帰宅と同時に抽出しておいたページをもとに、課題制作にすぐに取り掛かれます。

時間のうまい活用法だな

忙しい人にはうってつけの本です
そう。
私みたいなね!!!!
【実際に読んでみた】

課題制作が環境問題にまつわるものだったので、それに関係する親書を入手してきました
こちらです。↓
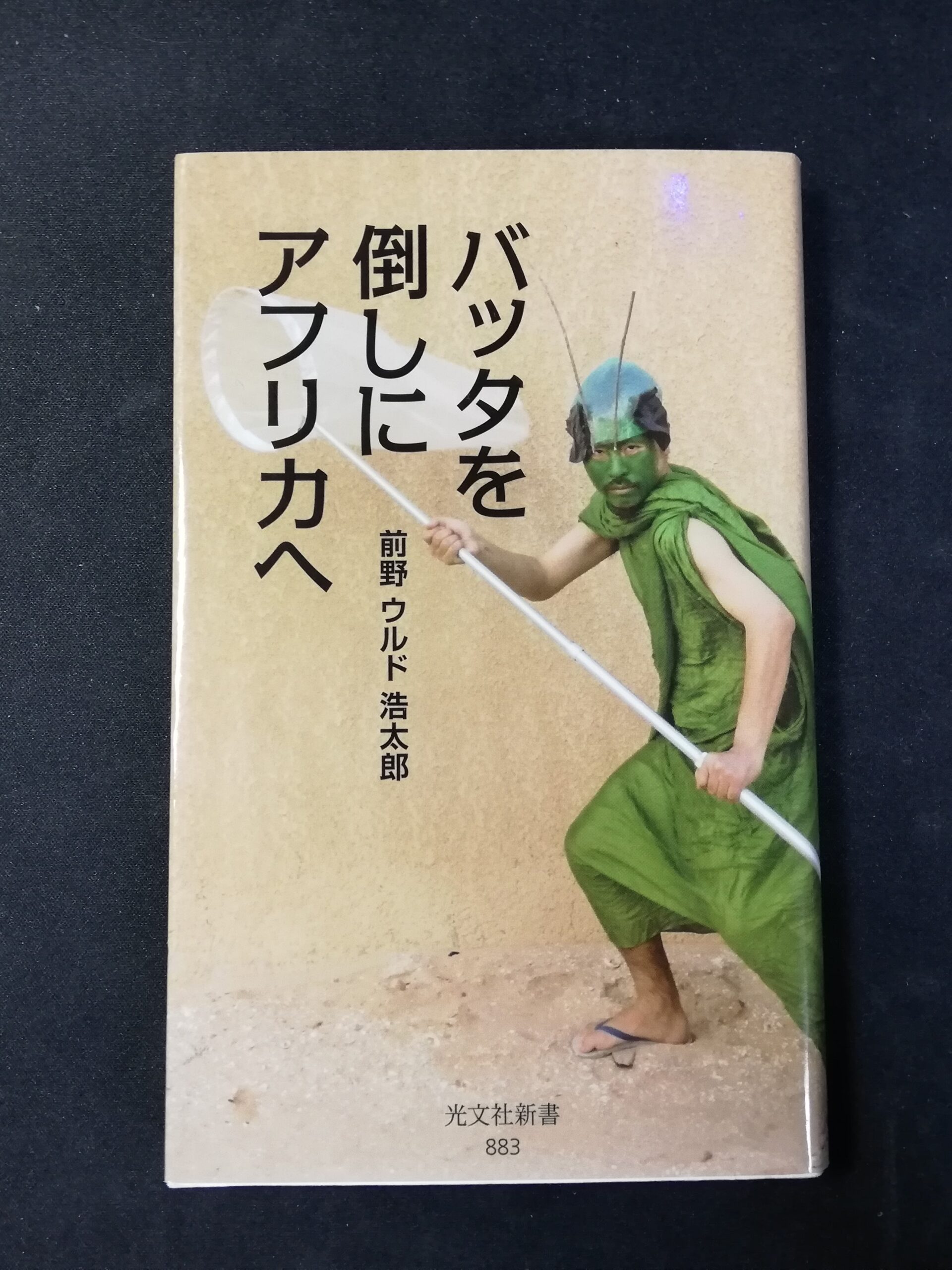
前述でご紹介いたしました、『バッタを倒しにアフリカへ』でございます。
バッタが好きだけれど、何かとバッタから避けられる一人の男が綴った、ノンフィクション作品です。
内容としましては、
- アフリカと日本の価値観のズレ
- 前野ウルド浩太郎 先生 の狂気じみたバッタへの執念
- 先人たちの努力と恩恵

環境問題について学ぶつもりでしたが、ウルド先生の語り調は感情がダイレクト掴むことができて、一つの物語として楽しめました
とくに、表紙をめくった瞬間の掴みが、恐ろしほど根深く印象に残っています。
『バッタを倒しにアフリカへ』というタイトルをしっかりと覚えてから目次を通り過ぎて、入りの文を読みますよね。
しかし、まさかあんなことを考えていたなんて……

なんだよ、めっちゃ気になるじゃん

そう、読み進めていると疑問が解決する気持ちよさと、新たな疑問のモヤモヤの波状攻撃を受けるんです
これがまた、工夫がされていました。
写真のないページの方が少ないというほど、現地の写真が掲載されています。
ですから、疑問のイメージと解決のイメージが簡単に想像ができます。

勉強だけでなく、一つの物語として面白い新書でした。
課題に取り掛かるぞ!!

よし!!
これで課題を厚みを持たせるネタがGetできました

じゃあ記事もそろそろ終わりか?
・
・
・
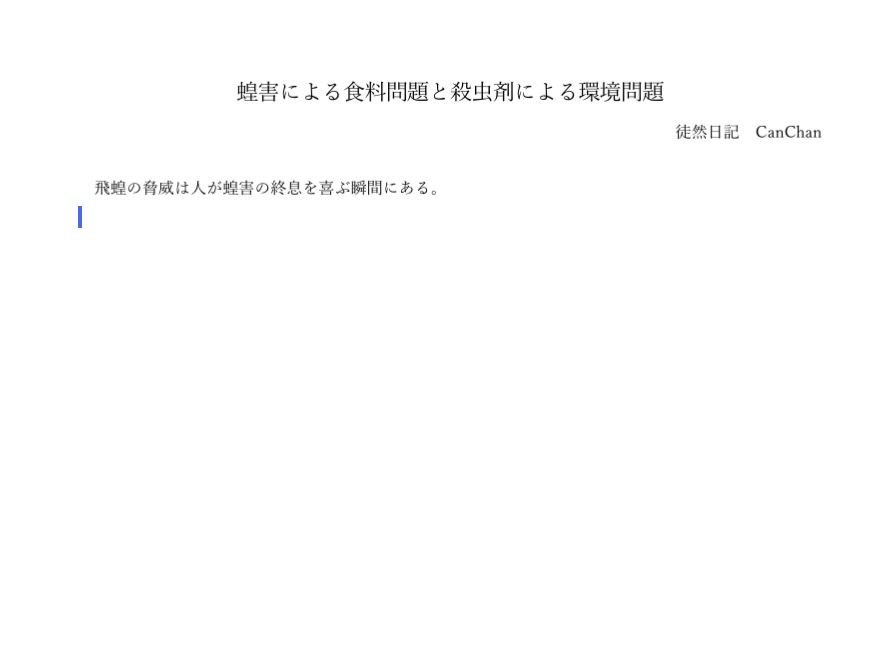
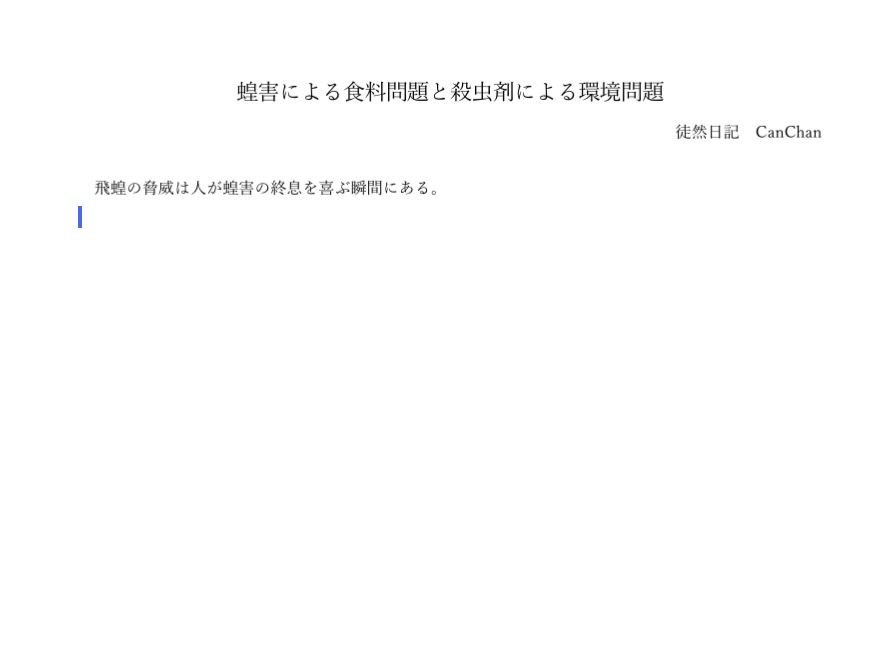
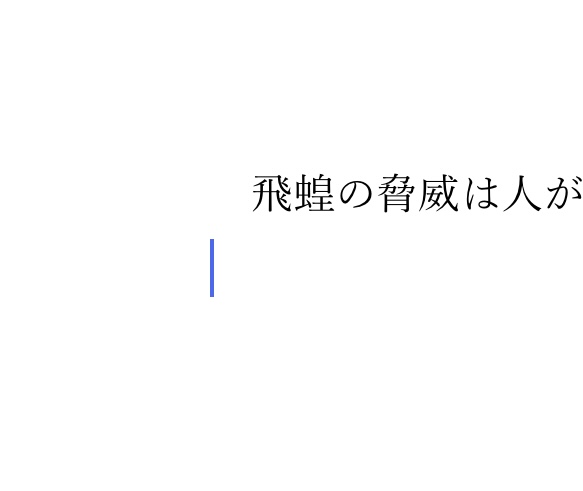
CanChanでした。
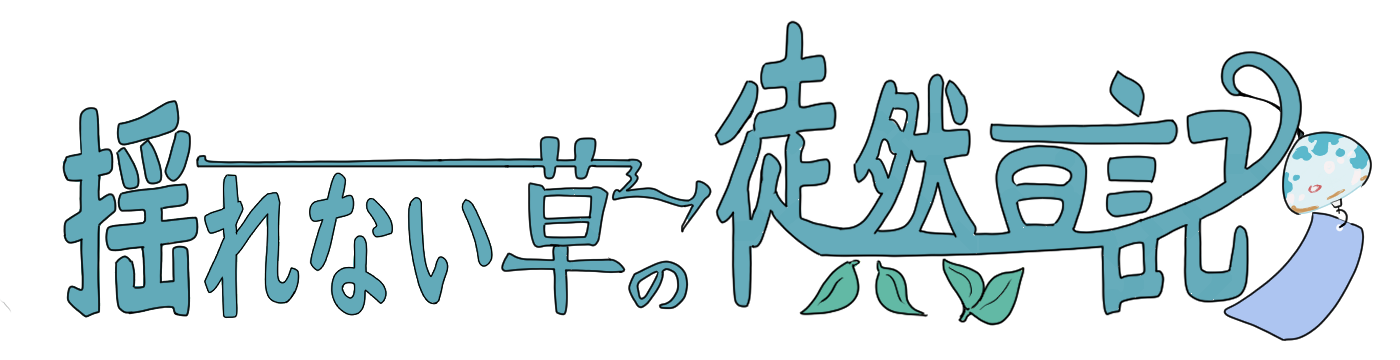
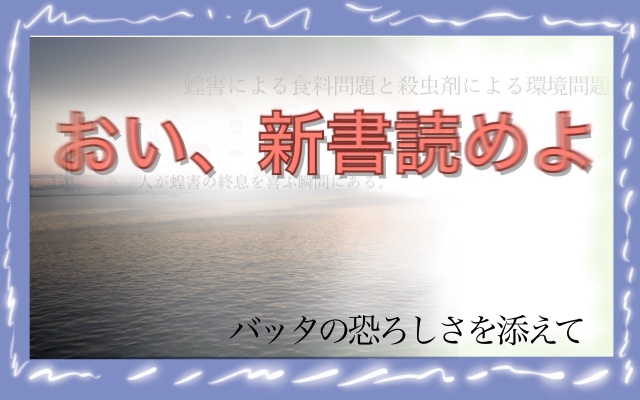

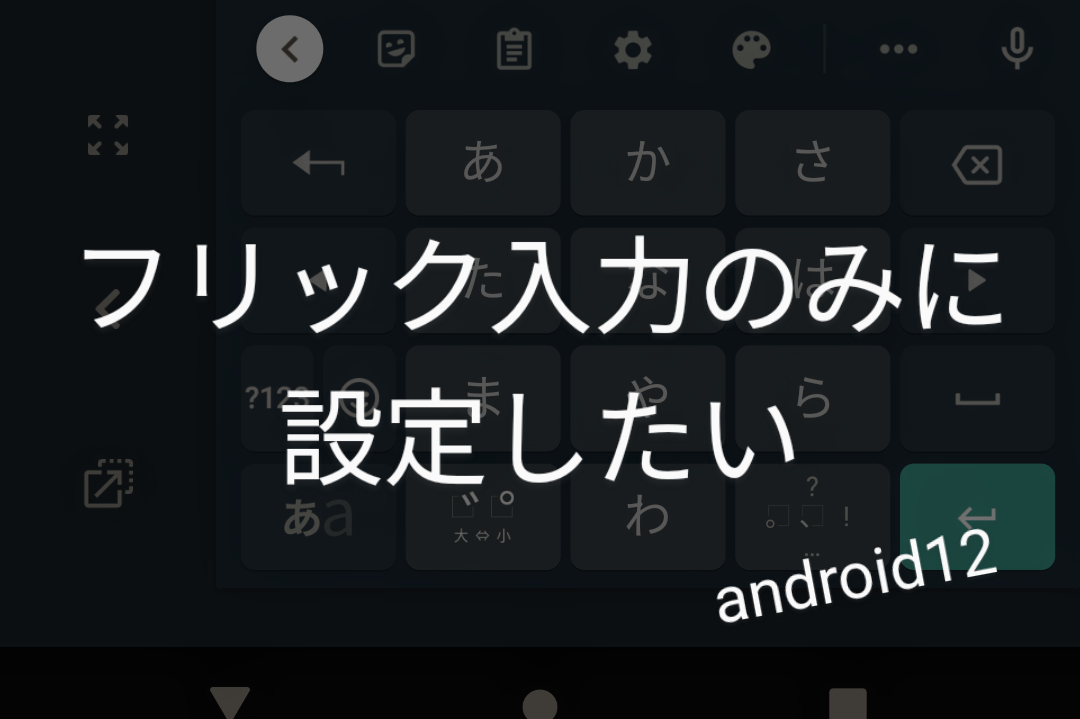
コメント