宵はいつも奈留の側。
宵の長い黒髪も深い黒目も夜空に溶け込むことなく、強い自我を発している。
奈留の短い白髪は夜の光を集めて、側に寄り添う小さな存在を照らしている。
しわのない白衣を纏う二人は、きんと透き通る冷気に身を寄せ合う。
吐く息は冷気に溶け込み、あっという間に境がなくなる。
屋根の上で二人は手を重ねて、熱を共有した。
しきりに求めるその心許ないつながりは、少し離れただけであっという間に不安が体を蝕む。
宵が今そうであるように。
この場所に至るまでに、二人はいつものように屋根上へ登ったはずだった。二回の角部屋にある窓から足をかけて、そこに登るのが常だ。
今日は少し奈留が上るのを手こずった。
心の迷いか否か、宵には関係ない。
ただ、少しだけ宵を待たせてしまった。
普段に増して宵が奈留を欲した身振りが良く示している。
そうしている時にも空は移ろう。
宵はしばらく夜空を眺めることなく目を閉じた。
寝てしまうことはない。しきりに奈留に重なる宵の手は動いていた。
奈留は特別何をするでもなく、宵が寄せる身を受け止めるだけだった。
しんと大気のが揺らぐ音と、脈動する音を肌で覚えかけた頃、宵は目を開きそのままゆっくりと首を傾けた。
「あ」
「あったね」
宵が呟き、奈留が頷く。
二人して見つけたのは、北極星。
周りの星と見紛うことなく、そこで爛々と輝いている。
さっと動く音がして、奈留は星から目を逸らし宵を見た。
手を伸ばしても届くはずがないのに、宵は空に向けて手を伸ばしている。
服が擦れて、寒いというのに露わになる腕が光に照らされ映し出される。
宵は真っ直ぐ手のひらを向けて伸ばしても届かない星を、まるでそこにあるかのように手のひらを丸めた。
光は消えない。
変わらず息をしている。
宵は冷え切った右手を左手で包み、また縮こまって奈留に身を預けた。
今夜は夜空が騒がしい。宵は奈留の左側から懐に顔をうずめた。
真っ白な布地に皺が広がる。宵はお構いなしにぐりぐりと全身を寄せる。
奈留は懐に密着する宵を割れ物を扱うかのように、頭に手を乗せる。
どちらが口を開くことなく止まった時間の中にいた。
しかし有限の時間が流れていることを月明かりが教えた。
月が地平線から手を伸ばし始める頃、塵が散ったような星々の鼓動が早まる。
二人にとってそれは些細なことだった。
宵は顔をうずめているから外の様子はわからない。
ただ感じるのはすぐ側の振動が、大きなまま一向に治る予感がないことだ。
芯から響く振動はまるで焦っているようにも思えるものだ。
宵の側でその振動を発しているのは奈留である。
奈留は囚われていた視線を空に戻して、震える唇を堪えて口を開く。
「そろそろ戻ろう」
宵は顔を上げて上る月に視線を合わせて、逡巡することなく頷く。
「そうだね」
二人は体を少しだけ離して、立ち上がった。
まだ冷め切ることのない体に熱りを宿すまま、屋根を一歩一歩下る。
奈留が先に、宵が後に続く。
そうして、灯りのない二階の窓から少しの出っ張りに足をかけて家の中へ戻っていった。
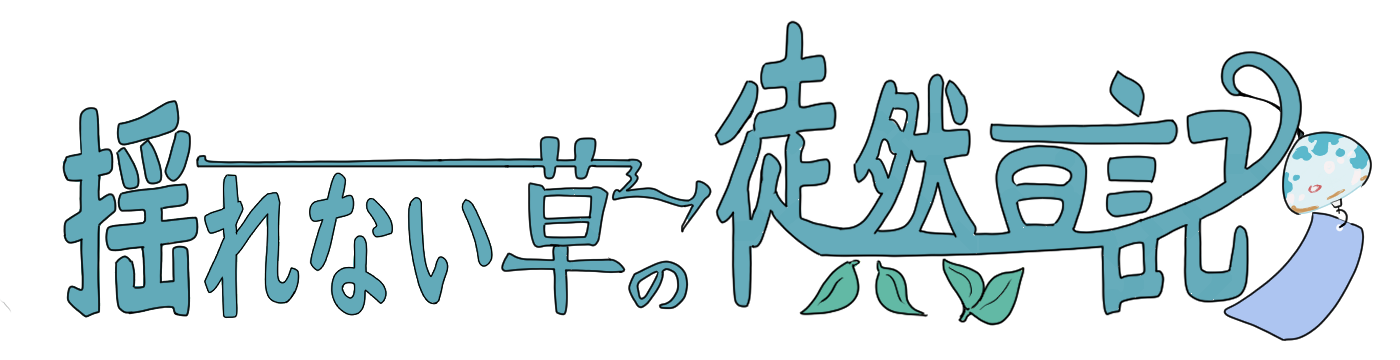
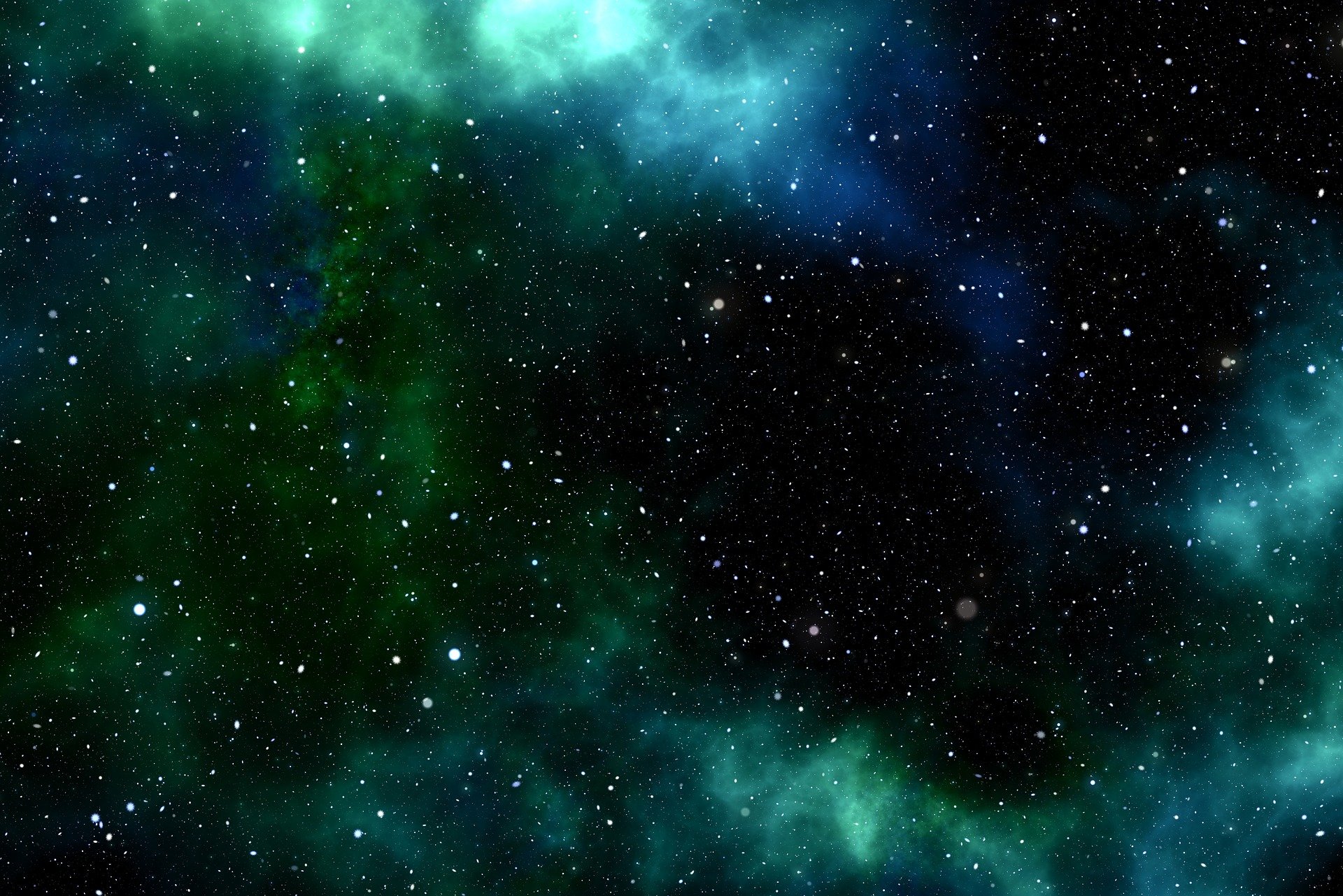


コメント