やる気°
記事の経緯
友人と久しぶりに会った。遠くでも上手くやっているらしい。場所が変わっても相変わらず今日を生きてなんぼのマインドで、精神面での耐久力に驚かされる。それだけ。
私も変わらず撮影することにした。今日のテーマは寄る。
撮影機材
寄るとは

写真撮影において「寄る」ことの効果とは何か。
私の好きで続けてきた経験から言うと、「主題を大きく見せることができる」という効果を得られる。
当たり前である。寄れば寄るほど写したいものが写真を占める割合が大きくなる。
そして、なぜ寄って大きく写したいのか。
何か物を注目してみる時に、前のめりになったり、目を細めたりして、繊細な輪郭を捉えようとする。
ものを大きく写すとその「注目」を強制することができる。作品として見てほしいものを見てもらうことができるのだ。

さて、これは何か。
私は度々目にして、毎年遭遇するものであるからすぐにわかる。
しかし、こうも小さく写してしまうと、これの主を含めなければ情報が伝わらない。
実はツバメの巣である。

私はものを撮るときに気を付けていることは、出来る限り新鮮な目線を探すことだ。
見たものそのまま写真を撮る「スナップ」も人々の日常に寄り添う形の作品として素晴らしいと思える。「街中スナップ」なんて、なおさらカメラ好きの写真だということが伝わる。
マクロ視点での写真撮影ではなくミクロ視点で写真撮影を考えた時、写真の撮り方は「癖」が出る。
私は、見ていて楽しい、伝えるのが楽しい写真を目指して写真を撮る。その時の「癖」を考えた時、私は「新鮮だから寄って撮る」のだと振り返ることができる。

この写真はアスファルトすれすれに伸びた草を写した。
こんな低い場所の葉を見ることはあったとしても、注目することはそうない。虫食いや光が当たりづらいような要因が合わさって、元気がないようだ。緑が色あせて黄色くなり生気が抜けている。
よく見るとこうした情報が分かるのだが、寄って写すと、より分かりやすい。

「寄る」ことはカメラレンズの特性を含めると、ぼかしのために重要な撮影テクニックであると言える。
この葉と「立った状態の人間の目の高さ」を比較すると、かなり高い場所に目がある。どうしても見下す構図になるのだ。
写真を撮ったときはどうだろうか。地面と葉っぱしか映らない。奥行きがない平面の写真になる。
私が撮影したい構図を掴むときに、奥行きを意識することが多い。
平面になるときは一旦寄ってみる。そうすると、ものを遠くから見るよりも舐めまわすように見ることになる。見る角度を変えることを繰り返すと、面白い構図が見つかる。
「奥行きとは寄ることの副作用的に表れる」ものだと言えるのではないだろうか。

私はこの花を捉えた時に、距離によって感覚が変わるなと思った。
遠くから見た時はたくさん花が咲いていると感じる。近くで見た時は、一つの花がこちらを見ていると感じたのだ。

もっと寄ってみた。しべの粉っぽさというか、やわらかさが分かる。

これ以上は寄れなかった。寄るのにも限界がある。
写真中央に注目してほしい。ヤモリがライトに張り付いている。
逃げるのだ。そういう時は仕方がない。限界の距離で舐めますだけにとどめる。

ただそういう時は、撮る。

デジカメの特権だ。フィルムにない強みを活かす。
寄る以上に、まずは撮る。撮って撮って撮りまくる。その過程で「寄る」を済ませる。

何でしょうこれ。

なんでしょうね。

まとめ
「寄る」のは構図探しに重要である。
沢山撮ることは寄ることにつながる。
寄ることは奥行きにつながる。
構図探しは簡潔に決められるものではない。
それではごきげんよう、CanChanでした。
あわせて読みたい
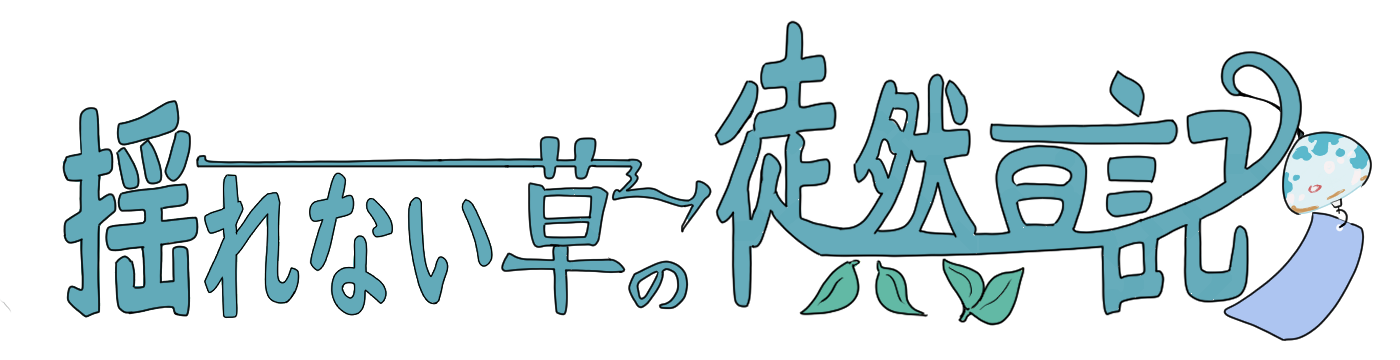





コメント