僕は真っ白なだだっ広い空間にいた。
ここがどこなのかとか、どこからここに来たのかとかはよく覚えてない。今さっきが自我が誕生した瞬間かのように記憶が欠落している。
周りを見ても何もわからない。ここにはなにもない。前後左右上下が曖昧になるかのような。きっと宇宙や無の中にいるときこんなイメージなんだろうな。
「この空間には前がある。」
気付けば隣に誰か立っている。ぽかんとしていると指を指して続ける。
「あれが前だ。」
指を指した先にはさっきまで認識できなかった扉があった。
色々納得できない。
「…まず、どちら様?」
「私のことはいい。ガイドみたいなものだ。あんまり重要じゃない。」
「ガイド?こんなになにもないのに?」
「扉をくぐればいろんなものを見ることになる。」
「いろんなものってなんだよ。」
「それはわからない。ただ何かは必ずある。それは進めばわかる。」
はあ。
いろいろ納得できない。
「ここは何なんだ?前ってなんだ?ガイドなのになぜ何があるかわからないんだ?」
「進めばわかる。」
進めと。それしか言わないのか。
進むしかないんだな。
ここには何もなくて、それ以外に取れる選択肢がなかったから。
「もしこの先が想像もできないような訳の分からない空間に繋がってたりしたらどうするんだ?進めるのか?」
「大丈夫。それは無い。」
無い?
「とにかく進めばいい。進めば理解できる。迷うことはないから。」
仕方なく、僕はただ進もうと決めた。
扉を開けると本屋が広がっていた。何の変哲もない本屋。
「ここは本屋?近所の……なんで?」
レジ前には売れ行きのランキングや映像化した本のコーナーが並ぶ。この奥には単行本の棚が、その奥に文庫本の棚があって、雑誌は右で絵本は左に…。
「っておい。ここは。」
ガイドを名乗る彼の方を見ると文庫本を物色していた。
「この小説、とても好きだった。この本の締めはとても雰囲気が良くて。始まりの~」
そのまま内容の解説を始める。
「主人公が変わっているように見えて、周りが変わっているんだよ。いやみんな変わってはいるけどね。出来事が起こるということはそういうことではある。でもね主人公が一番変わったなら周りが一番変えられると思わないか?」
「はぁ…何を言って…」
何を言いたいかはよくわからなかった。でもその感情は知っていた。僕はその本を読んだことがあった。
きっと言葉に出来ないんだろうな。僕もそうなんだ、言葉にできない本がある。棚を見回してそんなことを思った。
「やっぱりガイド向いてないんじゃないか?」
「…では寄り道はこの辺にして次の部屋に行こう。」
どこに進むのだろうか。あたりを見回す。そこでどういうことか、入り口の位置にうまく繋がっていないことに気づいた。やっぱりよく似た知らない場所だったんだ。窓の外には通っていた学校が見えた気がした。
「こっちだ。」
大人しくついて行くと本屋の奥に扉があった。
知っている本屋には似つかわしくないそのあまりにも周りから浮いて存在する扉を開ける。
「う。少し寒いな。」
扉の先は大きな川の土手だった。少し風が強い。
「ここは何も変わってないような気がするな。」
彼はどこか嬉しそうだった。
「変わってないって、知ってる場所なのか?来たことがあるのか?」
「来たことがあるとかないとか、そういうのはあんまり重要じゃないんだ。
ここの本質は空だ。大きく広がる空が主体だ。空は元素なんだ。人がいじくり回せるものじゃない。ほら見てくれ。」
わかるようなわからないような。確かに周りに高い建物はなく空はよく見えた。僕も空を見上げる。
まだ透き通るように青いが、少し暗くなった赤くない夕暮れのような空だった。見たことがない、でもどこかで見たような空だった。
そうか太陽がないんだこの空は。違和感はきっとそれだ。何かに照らされていてその何かが沈んでる。青がゆっくりと藍に変わる。
眺めていると少しずつ星が見える。まだ夕暮れで暗い星は見えないし星座も何もわからないけど安心する空だ。ああ、この星たちは。きっと確かにこの空は知っている空な気がした。
「…少しわかった気がする。」
「まだ眺めるか。今日もいい空だ。」
「いや。もう十二分に眺めたんじゃないかな。」
次の扉に歩き始める。
「ここは?」
この場所は何もない場所だった。屋内で前に扉が、左右に通路がある以外めぼしいものはない。
「…ここは?」
返事がないと振り返ると彼は微笑んで突っ立っていた。
「わかったよ。考えるよ。」
見た感じ前の扉は通ってきた扉と同じで次へつながっているようだ。
左右の通路は雰囲気は違うが、どこか似ている。よく見ると、共通して巧妙によく見えないようになっているのがわかった。一見直線的だけどなぜか見通せない。情報を見せないように工夫された道だと思った。
何処に繋がっているのか。この道はなんなのか。何があるのか。これ以上は進まないとわからないだろう。
「何もわからない。進むしかなさそうだけど、進んでもいいのかな。」
「……」
彼はここでは喋れないのだろうか。でも肯定してるように見えた。
モヤモヤしながらも扉を開けた。
入ったその部屋には布団がぽつんと敷いてあった。それ以外には何もなさそうだった。
「…寝るのか?」
「とりあえず入って見たらいい。寝るかどうかはそれでわかるだろう。」
どこか腑に落ちなさを感じつつも布団に入る。僕は首まで掛け布団をかけるタイプだ。だけど掛け布団をかける間もなく横になったあたりで瞼が重くなった。異質な睡魔に身を任せた。
僕は家にいた。子供の頃の記憶だろうか。家にベッドはなく僕はリビングの隣の和室に布団で寝ていて、そこからソファや食卓が見える。僕は一歩も動けない。頭だけが動かせて、自分の家で周りを観察する。リビングには誰もいない。嫌に静かで、なのに明かりはついている。やがて扉と窓が全て開いて風の通り道を金色の龍が通り抜ける。風が吹いているようで吹いてない。音も匂いも感じないから。そうか。入れ子構造なのか。
「朝だぞ。」
揺られて起きる。
「寝てたのか。」
確か夢を見てたような。昔の夢。道端の石ころのように大切なことを思いついた気がするんだけど。この場所での朝ってなんだろうと考えていたら寝ていたことは遠くに行ってしまった。
時間なんてないのに、起きるのが遅れたかのように急かされ扉をくぐる。
次は夜の海辺だった。後ろは山で、目の前には暗い海が広がっていた。周りは真っ暗でその代わりに上には満天の星空が広がっていた。ここで堤防釣りとかをしたら楽しいのかもなとふと思った。
「凄い田舎だなって感じがする。」
田舎でしか見れない明るい星空だ。
「ここはそういう場所なのかもな。非日常だったり、遠方の象徴なのかもしれない。」
「非日常や遠方の象徴?」
ガイドは星空を眺めながら言う。「ここはなんだか劇的だから。」
真っ暗闇なのにあまり恐怖感がないことに気づいた。はぁなるほど劇的か。例えば足を踏み外して海に落ちたら大変なことになるだろう。でも僕の中で僕がそれを映えると言っている。この星空のもとで海になることへの憧れがぼんやりと宿っている。そんなこと、本当は少しも思ってないだろうに。
「なんだか怖いな。不思議な場所だ。」
暗闇が海が怖いと思っているのにのんきにぼーっとできる。
「ここでなら死ねるか?」
「私は死にたいとは思わないな。やるとしてもエンディングを演じることかな。」
笑ってしまった。呑気な、乾いた笑いが出た。
「暗いの危ないから。早く進もう。」
扉を開ける。
扉を開けると白い花が一面に広がる花畑だった。どうやら海の近くの高台のようで遠くに海が見えた。満開に咲く花と緩やかでさわやかな風、遠くに見える綺麗な海に反して空だけがどんよりと曇っていた。
「せっかく花畑なのに、曇っている。なんだかどんよりした雰囲気になっている。」
「いやこれでいいんだスイセンは曇りの日にこそ眺めたいんだ。」
そう言うと彼はしゃがみこんで近くの花を観察し始めた。こんなにも沢山花があるのになぜ一つだけに着目するのか疑問に思った。よく見ると少し微笑んでいて、一輪の花を慈しんでいるのだと唐突に思った。
「何故、曇りの日に?」
「スイセンはそういう花なんだ。晴れの日に見てもいい。花は天候に影響を与えているわけではないし、皆好きな時に好きなように見ればいい。でも俺の中で暗い中で咲いているのがスイセンなんだ。俺の中ではそうなんだ。」
彼の微笑みが少し変わった気がした。何かを少しだけ後悔したのかもしれない。何か僕にはない感受性でこの花畑を見て、いろんなことを考えているんだと思った。それに僕はついていくことはできないと思った。
綺麗な花畑だ。でも僕にはその一輪一輪に寄り添うことはできないだろう。何故だろうか?知らない花だったからだろうか。なら今は?いやきっと上辺だけの行動になるだろう。それはそれで悪くないことだろう。ただこの空間において、それでは何かが足りないのだと思った。
彼の言うことはなんだかよくわからないままだったけれど、きっと僕は僕の中でスイセンが知らない花だったことを理解したんだ。僕はスイセンの花畑を後にした。進む。
扉を抜けると不思議な浮遊感を感じた。どうなっているのかわからない。光が…ないのか?自分の手足も見れない。確かに今通った扉も、くぐり抜けたと思った次の瞬間には消えていた。
あたり一帯が真っ暗で、気が狂いそうなほどの静寂が辺りを支配している。泡のようなイメージがぶくぶくと上へ向かってる。僕自身はゆっくりと落ちていくような。呆然として意識が溶けていくような。深海の底に落ちていくようなそれに、僕は圧倒されていた。
「そうか。ここに…」
ガイドを名乗った彼の声で我に返った。そうだ、ここはなんだろう。ここは…
聞こうと思った次の瞬間、彼はいなくなっていた。
は?
そこにはもうすでに何の温度も残ってはいなくて。
びっくりして見回しても周りには相変わらず何もない。彼の痕跡も。自分自身さえ。
そうか。彼は泡になったのだ。いや泡だったのだ。水面に向かう一縷の泡。でも水面なんてものはない。なら彼はまだそこにいて、一緒にいるのだろう。
なんなんだろうここは。ここは何で、何故ここにいて、何をすればいいんだろう。つまりはそれが大事であるのだろう。
しかしここは何もわからない、何にもなくて、無のような。そういう意味では一番最初の部屋に似ている。
周りを見ても何もわからない。ここにはなにもない。前後左右上下が曖昧になるかのような。でもここは深海というようなイメージの方が近い。白と黒、それだけが違うようでその実全く違う空間でもある。
ここは、透明で、暗くて、浮遊感があって、淡い圧迫感があって、孤独で静かで、ゆっくりで、何もなくて、少し冷たい。
そうかここは執着の行き着く先なんだ。執着の成れの果て。冷めた熱。ここは。
決まっていないゆえに決定した、僕の苦悩の、絶望の、希望の、理想の、深淵の、退屈の、無知の風景。
僕は笑っていた。僕も笑えるように。心地よい浮遊感に沈んでいく。僕はこの場所で想い馳せるだろう。僕はこの場所で溶けてなくなるだろう。一瞬で消える。永遠を過ごす。
僕はここで泡になったのだ。また、泡であったのだ。
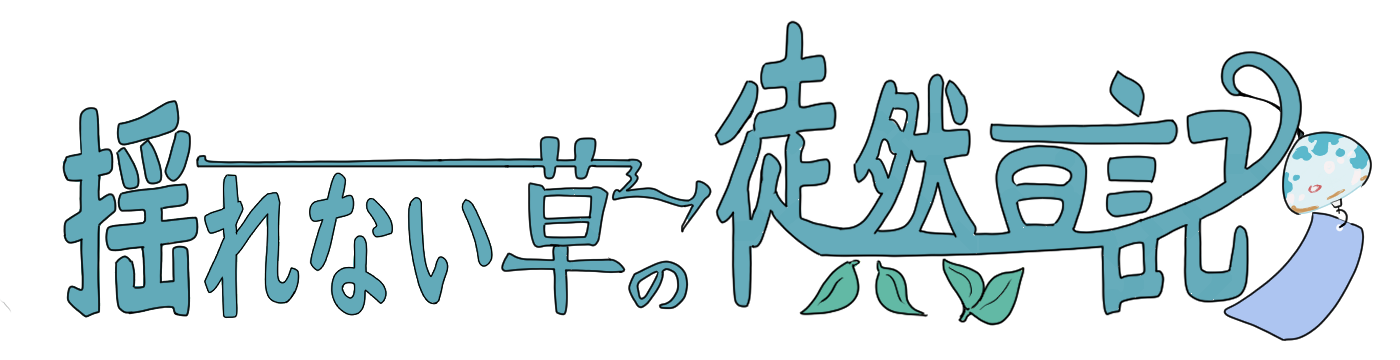


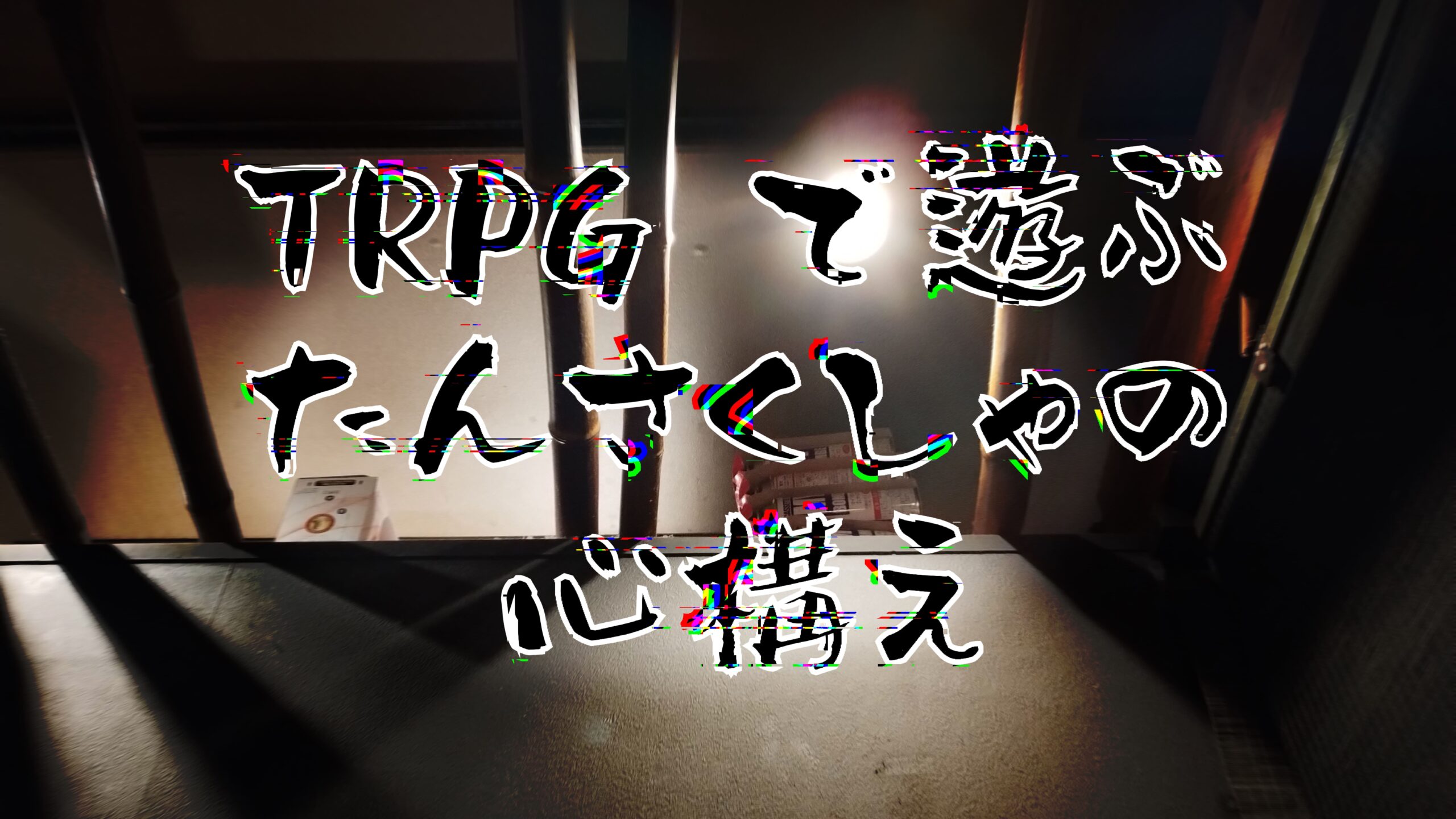
コメント